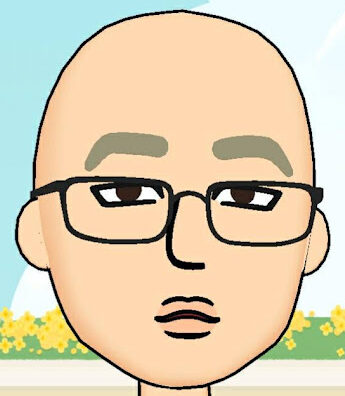令和7年12月5日(金)
4時起床 寒い 重ね着して寝ていたので布団の中では全然寒く無かった
靴下はいて寝ていた
今着ている上着は会社でよく着ていた 冬になると寒いので仕事以外の時は羽織っていた
寝るために朝早く会社に行って時は必ず着ていた 休憩所のエアコンだけでは寝るには寒さが厳しかったから ネックウォーマーも着けていた ダイソーで買ったものだけど中々よい
今日の予定は決まった 大宮に行ってアルファエックスが来るか確認
その結果をユーチューブの投稿に書く
もしアルファエックスが来る気配があったら配信を始める
配信終了後 2往復目は小山に行って小山で配信 今年はわからないが去年は2往復目は小山で停車したからだ でも時間も違ってたし今調べてみたら小山停車中の記事がポストされてなかった
通過の可能性高いな それでも出かけてみよう
もし電車来なかったら母の墓参り行く
22時46分 今日一日の終わりだ
9時32分の電車に乗り10時に大宮に着いたが16番線ホームに回送表示は出ていなかった
代わりに団体の表示が出ていた 時間も16時・・分 と出ていた
珍しい 新幹線ホームで団体列車の表示を見たのは初めてだな しかも時間まで出ていた
アルファエックスが来ないのが分かったので墓参り行くことにした
京浜東北線で北浦和へ 駅を出てから花屋へ向かうがまだ開店してなかった
花を買わずに墓に向かう 時刻調べなかったがちょうどバス停にバスがいて乗れた
バスを降りて約10分歩く 初冬の冷たい風 でも日差しが暖かく気持ちよかった
墓に着いて親戚の墓に線香をあげる 花が供えられていた
その後自分の両親の墓に行く こちらも花が供えられていた 線香を点ける
しばらく線香が燃えるのを見ていた 風が吹いて塔婆が揺れる
だれもいないのに誰かいるようなそんな気がした
昼間だし少し離れたところでは作業している人と音が聞こえるのになんかこわかった
塔婆がカタカタする音って嫌いじゃないんだけどなんか怖い
墓参りを終えて大宮に到着 時間は12時 混んでいるのわかってたけどサイゼ行く
さほど並ばず 10分程度で席に案内される お隣は学生君二人 スマホのゲームやってる
少しうるさい 前日もマックで英語の勉強してた時 4人組の学生君が来てスマホのゲーム始めてた 正直うるさく感じる 最近学生君との相性がいい
ビールとコーンスープ ドリアを注文 その後ワインとつまみを追加
めっちゃ楽しかった サイゼでワイン飲むときの時間が最近すごく楽しかったりする
ビールとは違ってゆっくり少しずつ飲んでいるからかもしれないが
店を出た後吉野家食べたくなったので向かった セットを頼む1000円也
美味しかった 今度は鍋を食べようと思う
帰宅の電車で寝てしまう 気が付くと地元の駅を発車したばかり やってしまった
次の駅で降りる 終点なので電車は降り返す 一度外に出て車両を変えて再び乗車
1つ先の地元の駅で降りる 駅員さんいなかったので ワンデーパスをポストの中にいれた
帰宅したら旅行中に買ったお土産届いてた
ものすごく眠くて 自室で寝る
先ほど起きた
今日の絵

One Short Story — “The Letter by the Lantern”
The village by the sea kept its lights low and its secrets softer. Mira arrived on a rain-scented evening, her suitcase small and her map folded like an apology. She had come for the quiet — the kind that lets you hear your own steps — and the town, with its narrow alleys and low roofs, welcomed her without asking why.
On her first night she noticed a lantern that always stood just where the harbor path turned. It glowed like a patient eye, and beside it lay a folded piece of paper, weathered at the edges. Mira picked it up because small things sometimes ask to be chosen.
The letter was short, written in a hurried hand: “If you find this, please return it to the Blue Door. — A.” There was a stain of salt on the bottom corner, and Mira thought of how many stories salt could hold.
The Blue Door belonged to an old café on the edge of the quay. Inside, the owner — a woman with warm eyes and hands that smelled faintly of cinnamon — made Mira a cup of tea and listened as if she had all the time in the world. Mira explained the note. The woman smiled and said, “Ah. A keeps leaving notes. He forgets that some things need to find people, not shelves.”
Over the next days Mira learned the rhythm of small repairs: a broken window, a lost cat, a sandwich left on a bench. Each time she helped, someone mentioned “A” and how his notes wandered like little paper boats. The town, it seemed, trusted those boats to reach shore.
The meeting itself was quiet. A was older than Mira expected, with hands that trembled slightly when he laughed. He had been coming back to the sea to remember something he could not hold in language. When he read the letter again, his voice was gentle: “I wanted to leave proof that I am still here.” Mira handed it back.
That evening they walked to the lantern, and A tucked a new note under its base — not a message for someone, but a small promise: “I will try to remember to stay.” The lantern swallowed the words and gave them back as light. Mira realized that sometimes quiet is not emptiness; it is space where two strangers can leave and keep what they promised each other.